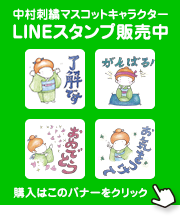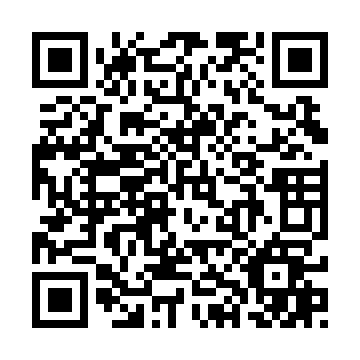HOME > 二十四節気のご紹介・十二支のご紹介・今月の花 バックナンバー
今月の花
-
蝋梅(ろうばい)
今月ご紹介させて頂く花は京都・浄福寺に咲いている蝋梅(ろうばい)です。
12月25日〜3月のまだ花の少ない冬季に咲き始め、とても良い匂いがします。
中国産で、唐の国からやってきた花という事から唐花とも呼ばれます。
花言葉は「ゆかしさ」「慈しみ」
この花言葉は花の少ない時期に黄色い花を咲かせる蝋梅の奥ゆかしく、控えめな姿にちなむとも言われています。
-
御会式桜(おえしきさくら)
今月ご紹介させて頂く花は京都・妙蓮寺に咲いている御会式桜(おえしきさくら)です。
別名「十月桜」とも呼ばれ10月頃から咲き始めて半年間ほどかけて4月に満開になるという珍しい桜です。
御会式桜の落ちた花びらを持ち帰ると恋が成就するという逸話もあります。花言葉は「寛容」「神秘的な心」

-
椿(つばき)
今月紹介するのは京都・興聖寺に咲いている椿(つばき)です。
日本や中国などの東洋地域を原産とし、古くから日本人に愛されてきました。
海外に渡った18世紀頃には東洋的で端正な美しさに『東洋の薔薇』という愛称まで付けられました。
ジュゼッペ・ヴェルディ作曲 オペラ『La traviata』の原作小説『椿姫』にも物語を象徴する花として登場します。白椿の花言葉は『申し分のない魅力』『完全なる美しさ』

-
金木犀(きんもくせい)
今月紹介するのは京都・相国寺に咲いている金木犀(きんもくせい)です。
原産地は中国南部。江戸時代に日本に伝わってきたと言われています。
元々はギンモクセイの変種です。花言葉は『謙虚』『謙遜』
強い香りが印象的な一面とは裏腹に、咲かせる花は、小さくつつましい様子にちなんでつけられました。
-
木槿(むくげ)
今月紹介するのは京都・千本釈迦堂に咲いている木槿(むくげ)です。
街路樹や公園の木に利用される事があり、見かける機会も多いと思います。木槿は、奈良時代から栽培されていたと言われる歴史の長い花です。
7〜10月に淡いピンクや白い花びらを咲かせます。花言葉は「新しい美」「信念」
「新しい美」は次々と新しい花が咲いていく様から付けられました。
「信念」の花言葉はタチアオイと同じです。木槿は『低いタチアオイ』という学名をもっている為、タチアオイと同じ花言葉が付けられました。
-
トレニア
今月紹介するのは京都・本久寺に咲いているトレニアです。
トレニアは耐陰性があり、夏にも花を咲かす事が出来る為、とても育てやすい植物です。
花壇の寄せ植えに利用される事が多く、耐陰性があることから、シェードガーデンにもよく使われている草花です。花言葉は『ひらめき』
トレニアの雌しべは先端に触れると閉じる特徴があります。
この特徴に俊敏さが感じられることから、「ひらめき」という花言葉が付けられました。
-
立葵(タチアオイ)
今月紹介するのは京都・相国寺に咲いている立葵(タチアオイ)です。
花言葉は「大望」「野心」「豊かな実り」「気高く威厳に満ちた美」
「大望」「野心」「豊かな実り」は立葵に多くの実が付く事から由来します。
「気高く威厳に満ちた美」は高く伸びた茎に咲く美しい花の姿に由来します。
アオイという名称は、葉が太陽の方に向かうことから「仰(あおぐ)日(ひ)」の意味があります。
-
金糸梅(キンシバイ)
今月紹介するのは京都・上御霊神社付近に咲いている金糸梅(キンシバイ)です。
花言葉は「きらめき」「秘密」「太陽の輝き」
花弁が完全に開ききらない事から「秘密」という花言葉が付けられました。
また「太陽の輝き」「きらめき」という花言葉は、金糸のように輝いて見える雄しべと鮮やかな黄色の花弁が、美しく輝く太陽を連想させることから付けられました。開花時期は6月上旬から7月の上旬まで初夏から夏へと移り変わる季節を知らせてくれます。

-
さつき
今月紹介するのは京都・大徳寺にあるさつきです。
え?さっき見たって? (-_-)/ナンデヤネン
花言葉は「節制」
初夏である5月中旬ごろが見頃となり、山奥の岩肌や石垣などに咲いています。
花が咲き始めると辺り一面に咲くのでとても華やかです。『つつじ』と呼ばれる花によく似ていますが、花や葉の大きさと開花する時期が違います。
さつきは5月中旬ごろに咲きますがつつじは4月中旬ごろになります。
つつじは花や葉が大きく、さつきは逆に花と葉が固めで小さいというのが特徴です。
-
イチハツ
今月紹介するのは京都・上御霊神社にあるイチハツです。
花言葉は「使者」「付き合い上手」
アヤメ科の一種で、アヤメ類の中では一番早く咲き出す事からイチハツ(一初)という名前が付けられました。
外側の大きい花びら(外花被)には、つけ根の部分から真ん中にかけて鶏の鶏冠のような白い襞があります。イチハツの学名【Iris tectorum】は、属名がギリシャ語のIris(虹)に由来しています。
花言葉の「使者」は、ギリシャ神話の虹の女神イリスが天上と地上を結ぶ虹の橋を渡って使者をつとめたことからきています。
-
枝垂れ桜
今月ご紹介するのは京都・本満寺にある枝垂れ桜です。
桜の語源は日本神話の女神コノハナノサクヤビメ(木花咲耶姫)のサクヤを取ったもの、咲くに複数形の「ら」を加えた、など様々な説があります。
平地では新年度が始まる3月〜4月に開花することから、人生の転機を彩る花にもなっています。枝垂れ桜は桜の種類の中で最も枝が長く、下に向かって垂れている所から「枝垂れ」という名前が付けられました。
桜の花言葉は種類によって変わり、枝垂れ桜は『優美』という花言葉を持っています。

-
水仙
今月ご紹介するのは京都中立売通に咲いている『水仙』。
花言葉は「うぬぼれ」「自己愛」です。
あまり良い花言葉では無いので、プレゼントの時は注意して下さい。春を告げる草花として古くから親しまれてきました。
スイセンの仲間はおよそ30種の野生種があり
スペイン、ポルトガルから北アフリカなど地中海沿岸に分布しています。球根の部分には毒があり注意が必要です。

-
白梅
今月ご紹介するのは京都御苑に咲いている『白梅』。
花言葉は「気品」です。古くから日本人に愛されてきた梅の花。
江戸時代以降の花見といえば桜ですが、奈良時代以前に「花」といえば梅のことでした。
平安時代、菅原道真が愛した花としても知られています。
道真とその神格化である学問の神、天神のシンボルとしても梅が使用されています。
-
寒椿
今月ご紹介する花は妙蓮寺に咲いている『寒椿』。
花言葉は「謙譲」「愛嬌」です。椿よりも早く寒い時期(12月〜2月)に咲く花なので『寒椿』と名づけられました。
かなりの日陰でも花を咲かせる控えめな姿から【謙譲】の花言葉が付けられています。
-
山茶花
今月ご紹介する花は白峰神宮に咲いている『山茶花』。
花言葉は「困難に打ち勝つ」「ひたむきさ」に加え色によって花言葉が変わり
白:「愛嬌」「理想の恋」「あなたは私の愛を退ける」
ピンク・赤共通:「理性」「謙遜」
赤:「あなたが最も美しい」
ピンク:「永遠の愛」椿とよく似ているため間違われる事が多いのですが、椿よりも小ぶりで花弁が細長い形をしています。
古くから日本人に愛され、厳しい冬にも関わらず花を咲かせる姿からひたむきな姿を表わす花言葉を持っています。
-
紫式部
今月ご紹介する花は紫式部墓所に咲いている『紫式部』。
花言葉は聡明・上品・愛され上手・知性・賢さ。紫式部は、通称名は藤(ふじ)式部と呼ばれていましたが、『源氏物語』中の女主人公、紫の上に 因み、紫式部と呼ばれるようになったそうです。
物語は「桐壷」から始まる54帖からなり、光源氏の誕生と栄華、その晩年の苦悩、その死と子らの悲哀を描く三部構成になっています。
紫式部は、自らの半生を物語に投影したといわれていて、12年の歳月をかけ、完成とともに亡くなられたそうです。
-
彼岸花
今月ご紹介する花は相国寺の『彼岸花』。
花言葉は「情熱」「悲しい思い出」「独立」「再会」「あきらめ」。お彼岸の頃に咲く事から「彼岸花」と名付けられましたが「曼珠沙華」「天蓋花」「狐の松明」「葉見ず花見ず」など様々な名前で呼ばれています。

-
百日紅
今月ご紹介する花は本法寺の『百日紅』
花言葉は「雄弁」「愛嬌」夏、枝先に群がり咲くサルスベリの花。花言葉の「雄弁」は、その華やかな咲き具合に由来します。
花名のサルスベリは、樹皮がツルツルで猿が登ろうとしても滑ってしまいそうな事に由来しますが、実際には滑ることなく簡単に登ってしまうそうです。
-
芙蓉
今月から近所の花をご紹介していきたいと思います。
今月ご紹介する花は妙蓮寺の『芙蓉』
花言葉は「繊細な美」「しとやかな恋人」朝に花が咲いて夕方にはしぼんでしまう1日花ですが、長期間ずっと美しい花を咲かせ続けます。
昔から美しい顔の事を「芙蓉の顔」と言い、芙蓉のように美しい顔ということを意味しています。
そのことから、芙蓉は美しさを褒め称える意味を持っています。
プレゼント(特に女性)に芙蓉を送る時、上記の花言葉を添えれば喜んで貰えると思います。
二十四節気のご紹介 バックナンバー
-
立夏
新緑の季節で、九州地方では麦が穂を出し、北海道では豆の種まきが始まります。 蛙が鳴き出すのもこの頃。
夏といっても、本格的な夏はまだ先。日差しが強くなり気温が高くなる日もありますが基本的には暑くもなく寒くもなく、湿度が低く風もさわやか。とても過ごしやすく、レジャーやピクニックなどに最適な季節となります。

-
穀雨
穀雨は4月20日頃および立夏までの期間。
春季の最後の節気です。
春雨が百穀を潤すことから名づけられたもので、雨で潤った田畑は種まきの好期を迎えます。
南の地方ではトンボが飛び始め、冬服やストーブとも完全に別れる季節です。
-
清明
清明(せいめい)は、二十四節気の第5。4月5日頃(2015年は4月5日)および穀雨までの期間。
春先の清らかで生き生きとした様子を表した「清浄明潔」という語を略したもので、様々な花が咲き乱れ、お花見シーズンになります。
-
雨水
雨水は2月19日頃(2015年は2月19日)および啓蟄までの期間です。
立春から数えて約15日目。
空から降るものが雪から雨に変わり、氷が溶けて水になる、という意味を持ちます。
草木が芽生える頃で、昔から農耕の準備を始める目安とされてきました。
春一番が吹くのもこの頃です。
地方によっても違うようですが、この日に雛人形を飾ると良縁に恵まれるといわれています。
-
春分
春分は。太陽がちょうど黄径0度(春分点)に到達した瞬間の事を指し、昼と夜の長さがほぼ同じになります。
この日から夏の終わりまで、昼がだんだん長くなり、夜が短くなります。
ヨーロッパなどでは、春分をもって春の始まりとしています。今回の画像は春分の頃に咲く「タンポポ」
黄色い花を咲かせ、綿毛のついた種子を作る事で有名。
子供の頃に綿毛を飛ばして遊んだ人も多いかと思います。
生命力の強い植物でアスファルトの裂け目から生えることもあります。
古典園芸植物の1つで、江戸時代幕末には園芸化され数十の品種がありました。
朝花が開き、夕方花が閉じます。
-
啓蟄
啓は「ひらく」、蟄(ちつ)は「土中で冬ごもりしている虫」の意味で、大地が暖まり冬眠していた虫が、春の訪れを感じ、穴から出てくるという意味があります。
二十四節気について書かれた古書「暦便覧」には『陽気地中にうごき、ちぢまる虫、穴をひらき出ればなり』と記されています。
今回の画像は啓蟄の頃に咲く「春蘭」。
この花は食用にもなり、塩漬けした花をお湯に入れて飲む「蘭茶」のほか、花を茹でて酢の物にして食べたりもします。
-
立春
今年は二十四節気を順番に紹介していきます。
立春は2月4日頃
および雨水までの期間。旧暦の正月の節。立春が一年の始めとされ、決まり事や季節の節目はこの日が起点。
八十八夜、二百十日、二百二十日も立春から数えます。暦の上では旧冬と新春の境い目にあたりこの日から春になります。
梅の花が咲き始め、春の始まりとなります。「寒中見舞い」は立春の前日まで。以降は「余寒見舞い」(2月下旬頃まで)になります。

十二支のご紹介 バックナンバー
-
干支 亥
猪の肉は、万病を防ぐと言われ、無病息災の象徴とされています。
亥年の人は大らかな性格。思い立ったら何が何でもやり通す頑張り屋。
ただ大ざっぱな性格が失敗に繋がる事もあります。
-
干支 戌
戌は犬であり、最も人間と深く結びついた生き物で、一番初めの家畜として狼から改良されて飼いならされ、人間に実に忠実であるとされています。
戌年の人はずるいことや嘘を嫌う誠実な性格と言われています。信頼関係を重んじ、社会性があり、人との絆を大事にします。

-
干支 酉
酉は鶏を表し神様へ新年のご挨拶に向かった十二支の動物の内
猿と犬の喧嘩を仲裁する為に猿と犬に挟まれた10番目の干支になりました。時を告げる鳥は鶏だけであり、人間に時を知らせる生き物として昔から大事にされてきました。
その規則正しい行動から、酉年の性格は、計画性があって几帳面、無駄がなく合理的。
財を成す人も多いと言われていますが、芸術にも才能があると言われています。
-
干支 申
猿は山の賢者で山神の使いと信じられていました。
信仰の対象としても馴染み深い動物です。
申年の人は器用で臨機応変と言われています。
この刺繍のモチーフは「三猿」と言われ「見ざる、言わざる、聞かざる」のことわざを表しています。

-
干支 未
未は家族の安泰と平和の象徴と言われています。
馬と同じく古くから人間と馴染みの深い動物であり、世界各地に羊との関連ある言い伝えやことわざなどが残っています。
未年生まれは穏やかで人情に厚いと言われています。
「未」の字は、象形文字で木の枝葉の茂った様を表し、未の月にあたる6月は様々な作物が成熟する大切な季節であり豊作への願いが込められています。

-
干支 馬
午は馬に当たる干支で、古くから人間と馬の関係は深く、家畜・労働力としてとても役に立つ生き物であり、戦の時には機動力として軍馬は絶対不可欠なものでした。
干支の由来は、7番目に神様の御殿に着いた事から、十二支の7番目になったとされています。
午年の方は明るく流行に敏感で開放的
頭の回転が良いのも午年の特徴とされ、社交的な部分がありますから人気者になるとされています。
配偶者運が大変よく、パートナーによってどうにでも変わっていく宿命を持っています。
結婚してから才能に目覚めていろいろな方面に活躍する人が多いと言われています。
-
干支 巳
古来より、蛇は信仰の対象でした。
知恵、財産をもたらす神様として崇められ、祭祀や祀りごとの「祀」に「巳」が用いられています。
「祀」とは自然神を祀ることをいい、自然神の代表的な神格が巳(蛇)だったからです。執念深いと言われる蛇ですが、恩を忘れず、助けてくれた人には恩返しを行うと言われています。
白蛇を助けた漁師は蛇の恩返しで大金持ちになったという逸話があります。
-
干支 辰
辰(龍)は信用と正義感の象徴とされています。
古来中国では権力の象徴として扱われました。古来より龍は高貴の象徴とされており、皇帝のみが使う事を許された文様とされています。
十二支の中で辰(龍)のみが空想上の動物ですが、その理由は諸説あり明確な答えが出ていません。
-
干支 兎
兎は温厚さと従順の象徴
穏やかな様子から家内安全、跳躍する姿から飛躍を表します。
古代中国では、白兎は瑞兆(非常に良いことのある兆し)として称えられていました。
ピョンピョン跳ねるうさぎのイメージから株価が上昇する年と言われています。
実際に1999年の株価は1年で37%高騰しています。
-
干支 寅
その昔、虎は天に輝く星であったという言い伝えがあり、その美しい毛皮が夜空の星に例えられ、「枢星散じて寅となる」という言葉が残っています。
五黄の寅年生まれの人は一般に運気が強いとされ、この年に女子が産まれることを忌む俗習があります。
五黄の寅は36年に1回訪れ、前回は1986年、次回は2022年となります。また「寅」の字は、“万物が演然としてはじめて地上に生ずる”ことを意味し、ここから寅の字は「始まり」を意味します。

-
干支 丑
丑は牛を指し、古来より人間と深く馴染みのある家畜のひとつで、大事な食料であり、農作業や運搬などの労働力であった牛は、社会とも密接に関っています。
神様への新年の挨拶へいち早く行動し、歩みが遅いながらもゆっくりと着実に進んで行き、誰よりも早く神様の御殿に着きました。
一番乗りはねずみに持っていかれましたが、粘り強さがある事と、努力家である事は認められ、干支の2番目の動物となりました。
その為、丑は粘り強さと誠実の象徴とされています。
-
干支 子
今年は十二支の作品を紹介していきます。
神が十二支の動物を決める際、家の門の前に来た順番に決めることにしました。
牛は動きが遅いからと真っ先に出かけ一番に門の前に着きました。
しかし、門が開けられる時に牛の頭の上に乗っていた鼠が牛の前に飛び出たので鼠が一番になりました。
なお、猫も十二支に入れてもらおうと準備をしていましたが、鼠が集合の日をわざと間違えて教えたので十二支に入ることが出来ませんでした。
それで今でも猫は鼠を追いかけ回すのだと言います。
今月の花 バックナンバー
-
2013年12月の花
東本願寺の枳殻邸の近くに有る文子天神で撮って来ました。
紫紺野牡丹と言う花です。
くねくねと伸びた雄蕊が印象的です。野牡丹の一と日の命けさあえか
富安風生
-
2013年11月の花
コスモスと言えば沢山群れさいているものですが近くの小学校の校庭に二、三輪淋しく咲いているのを一輪撮って来ました。
コスモスの高さを渡る風の色
稲畑汀子
-
2013年10月の花
この花はあちらこちらで良く見受けられる花です、堀川上立売のバス停の近くに咲いていました。
ずっと名前が判らずにいましたが、最近やっと判りました。
「チロリアンランプ」又の名を「浮釣木(うきつりぼく)」と言うそうです。
やっと名前が判って胸のつかえが取れました。提灯花想いの先を微かにも
作者不詳です。
-
2013年09月の花
朝咲いて夕暮れには落ちるところから朝開暮落花(ちょうかいぼらく)と言う別名が有ります。
此の木槿は家の近くの通称むくげ地蔵と呼ばれるお寺の花です。
木槿が咲き乱れる中に見つけられたお地蔵様が本尊として祀られています。小さなお寺です。木槿垣何時も洩れ来る同じ曲
稲畑廣太郎
-
2013年08月の花
去年の8月も百日紅(さるすべり)でしたが夏と言えばやっぱり百日紅です。町のどこを歩いても此の花を目にします。
去年は少し淡いピンクの花でしたが、今年はしっかりした色の花です。咲き満ちて天の簪百日紅
阿部みどり女
-
2013年07月の花
秋の七草の一つと言われている桔梗ですが、ご近所の鉢植えで咲いていました。
蕾も多い事ですので、次々咲くのが楽しみです。
異常気象が言われている中こんな事も有るかなと思っています。かたまりて咲きて桔梗の淋しさよ
久保田万太郎
-
2013年06月の花
今月の花は、ヤマボウシ(山法師)です。
名古屋教室の隣の、名テレ(テレビ局)の前に咲いていました。8月〜9月頃には、赤い実をつけマンゴウのような甘さのある実で果実酒に適しているようです。又その頃写真を撮って来たいと思います。山法師咲けば記憶のある山路
稲畑汀子
-
2013年05月の花
上御霊神社(京都魔界パワースポットの一つ)の小さな堀に咲いた「イチハツ」です。
アヤメ属のなかで一番先に咲くところからこの名があると言われています。此の花が咲くともう夏です。一八の白きを活けて達磨の絵
正岡子規
-
2013年04月の花
今御所は色々な花で賑わっています。
其の中でもひときわ大きく立派に白木蓮が咲き誇っています。木蓮に日強くて風さだまらず
飯田蛇笏
-
2013年03月の花
妙蓮寺の御会式桜(おえしきざくら)です。
10月13日の日蓮大聖人御入滅の日、前後から咲き始め、年をまたいで、4月8日のお釈迦様の聖誕日ごろ満開となる珍しい桜です。
この桜の散った花びらを持ち帰ると「恋が成就」すると言われています。決して、枝を手折るようなことはしないでください。手折った恋は実りません。
先日テレビで紹介されていましたので、ご覧になった方も多いかと思います。

-
2013年02月の花
今月の花は山茶花です。
私共の近くに沢山花をつける山茶花が有ります。
冬場の花の少ない時期に長い間楽しませてくれます。
まだ蕾も沢山有りますので、これからもどんどん開いてゆきます。山茶花や金箔しづむ輪島塗
水原秋桜子
-
2013年01月の花
今回の花は、今宮神社の隣のあぶり餅を売る店に飾って有った水仙と椿、千両です。
どの店にも餅花を飾ったり、松を活けたりしてお正月を祝っています。水仙を生けしこころに習いけり
後藤夜半
-
2012年12月の花
ピラカンサス
花言葉は、愛嬌、燃ゆる想い、快活今月も花ではなく実です。
我が家のすぐ近くに毎年真っ赤な実を楽しませてくれます。
花は白くて小さいのでうっかり見過ごしてしまいます。
どの俳句歳時記にも季語と記されていませんが。
ネットでこんなのを見つけました。小春日や何故季語でないピラカンサ

-
2012年11月の花
芙蓉の花に続いて、今月は芙蓉の実です。
此の実が熟しきると、きれいに五つに裂けて種子が飛散します。
そんな折、かすかな音がして秋の深まりを感じさせます。竹生島見えて吹かるる芙蓉の実
森登雄
-
2012年10月の花
一年に一度登場する芙蓉ですが、今年の芙蓉は妙蓮寺の芙蓉です。
妙蓮寺は芙蓉で有名なお寺です。
他には毎月十二日に手作り市が開かれ大勢の人で賑わいます。開け放つ障子の陰や芙蓉咲く
高浜虚子
-
2012年09月の花
我が家のすぐ近くの白峰神社で見つけた珊瑚樹を紹介させて頂きます。
夏には白い小花が穂状に咲いて、秋には真紅に実が熟し其の色合いを珊瑚にたとえた名前で、有る程度老化しないと実はつかないです。珊瑚樹のいただきくらきまで熟す
古舘曹人
-
2012年08月の花
百日紅と言えば紅の花が多いのですが近くの幼稚園に淡いピンクの百日紅が見事でした。花期が長いので百日紅の漢名が有ります。
滑らかな幹は猿も滑り落ちるので猿滑(さりすべり)と名づけられました。ゆふばえにこぼるる花やさるすべり
日野草城
-
2012年07月の花
「これを庭中に植ゆれば火災を避くべく、はなはだ験あり」
(滑稽雑談)に説かれている縁起木である。
夏に米粒のような白い花が咲き
冬には赤く熟す実が美しく賞せられる。南天の花の薄日に水見舞
中村汀女
-
2012年06月の花
お隣の清楚な額紫陽花
中心の小さな粒粒の花を取り囲む様に四弁の花が咲くところから額の花とも言います。
紫陽花の華麗さに較べて清楚で素朴な感じが愛されます。この頃の雨読晴読額の花
鷹羽狩行
-
2012年05月の花
アヤメ科の花でとても繁殖力が旺盛で半日陰の湿地帯で咲く花ですが 乾燥地でもどんどん繁殖していく花です。
堀川今出川のバス停で見つけました。紫の斑の仏めく著莪の花
高浜虚子
-
2012年04月の花
今月は片栗の花を図案にして刺繍した作品です。
「もののふの八十をとめ等が汲みまがふ寺井の上の堅香子(かたかご)の花」(大伴家持) と万葉集に詠まれた堅香子の花は片栗の花の事です。片栗の一つの花の花盛り
高野素十
-
2012年03月の花
身の回りに花の少ない昨今、今日は植物園の「早春草花展」を見てきました。
プリムラポリアンサ(桜草)花屋の店頭で良く見かけますが、それが赤いハート型で周りを黄色や青のハートが取り巻いています。わがまえにわが日記且桜草
久保田万太郎
-
2012年02月の花
華やかな桜にくらべ清楚で気品高くどの花にも先駆けて咲く梅は昔から和歌や俳句に良く詠まれています。
初天神の梅まだちらほら程度しか咲いていませんでした。梅が香にのっと日の出る山路かな
芭蕉
-
2012年01月の花
京都には珍しい雪の朝、白峰神社にて。
南天の実は中国では聖竹と称して正月に寺廟の祭壇に供えたり家や船の中に飾って新年を祝いました。
日本でもお正月の床飾りの花材に用いられます。実南天鴎外生家北向きに
松崎鉄之介
-
2011年12月の花
石蕗の花(つわのはな)
葉は光沢が有ってふきの葉に似ている事から
艶葉蕗(つやはふき)とされ訛ってつわぶきと言うそうです。
漢名では 吾(とうご)の花と言う。
吾(とうご)の花と言う。
お寺の庭に良く見かけます。
これは智積院の花です。静かなる月日の庭や石蕗の花
高浜虚子
-
2011年11月の花
紫式部、何と優雅な名前を貰っている事でしょう。
花言葉は、「愛され上手」「上品」「聡明」等が有るようです。
六月七月花の頃は、うっかり見過ごしていますが、実紫になると目を引きやすいようです。
正式には「コムラサキ」なのだそうです。雨後いまだ雲のたゆたふ実むらさき
能村登四郎
-
2011年10月の花
お彼岸ともなれば、畔に燃えるように咲く曼殊沙華、茎に毒を持っている性か花の形の性か何か人に嫌われるところが有るが、真っ赤に燃える情熱的な花だと思います。
相国寺の花です。曼殊沙華落暉も蘂をひろげけり
中村草田男
-
2011年09月の花
蓮は仏陀の国インド原産と聞きます。
先年聞いた話、二千年前の遺跡から発見された
蓮の実が見事に発芽し今では各地で栽培されていると言う
なんともめでたい限りです。此の蓮は相国寺の蓮です。さわさわとはちすをゆする池の亀
鬼貫
-
2011年08月の花
今月の花は相国寺に咲き始めた芙蓉です。
芙蓉の花はしばしば美女にたとえられます。楚々として艶麗しかも花は一日でしぼみ、あっけなく落ちる風情が美人薄命に通じます。物かげに芙蓉は花をしまひたる
高浜虚子
-
2011年07月の花
今年は去年にもまして暑さのきびしい夏になりそうです。六月から三十度をこえる暑さが続き、雨も降らないので、家の近くの花々がとても疲れているようです
ようやく見つけた少し元気な金糸梅(きんしばい)二輪月の出のなまめくあたり金糸梅
加賀谷杵子
-
2011年06月の花
五月・六月は花がいっぱいの時期
ご近所では皆さん丹精されましてバラ、牡丹、らん、石楠花、芍薬、等々、花盛りです。其の中の一つ、鉢植えの芍薬を撮って来ました。芍薬の花にふれたるかたさかな
高浜虚子
-
2011年05月の花
今年は未曾有の災害と思われる大災害に心がうばわれている間に春はどこかに行ってしまいました。
早くも杜鵑花(さつき)の花が目につきはじめました。満開の杜鵑花(さつき)の庭の片翳り
小出秋光
-
2011年04月の花
暖かさも行きつ戻りつする中、歴史的にも有名な一条戻り橋のほとりに、山桜が見事に咲きました。周りの桜はまだとても蕾がかたいようでした。
うかれける人や初瀬の山桜
芭蕉
-
2011年03月の花
水仙郷といえば何といっても淡路島に越前海岸ですが、この水仙は、私共のすぐ近くの路傍にひっそりと咲いていたものです。
昃(ひかげ)れば水仙の香は地に沈み
楠本憲吉
-
2011年02月の花
今年の冬の寒さは、又格別の寒さの中、春にさきがけていち早く北野天満宮の梅が咲きはじめました。
2月の梅花祭りには、見事に咲きそろい、馥郁たる香りをはなつ事と思われます。梅一輪一輪ほどの暖かさ
嵐雪
-
2011年01月の花
今月の花の山茶花も御所で撮ってきたものです。
山茶花は10月頃から咲き始め、翌年の2月頃まで咲いては散り、散っては咲きを繰り返し、長い間花が楽しめるので、庭木に好んで植えられます。山茶花のここを書斎と定めたり
正岡子規
-
2010年12月の花
暑かった夏から急に寒くなったためか、今年の紅葉は特に紅が美しいようです。
京都市民のこの上ない癒しの場所、御所の紅葉です。かざす手のうら透き通るもみじかな
大江丸
-
2010年11月の花
赤のまんま(犬蓼 いぬたで)
雑草のように咲いているが可憐な花で
女の子がまゝ事遊びに赤飯になぞらえる
俳句や短歌に良く詠まれている此辺の道はよく知り赤のまゝ
高浜虚子
-
2010年10月の花
【9月26日】
今日は絶好の行楽日和。
植物園に行ってきました。鶏頭の強烈な赤に思わずシャッターを切りました。
鶏頭の十四五本もありぬべし
正岡子規
-
2010年09月の花
今年は夏バテに良いゴーヤが例年の3倍の売れ行きだそうです。
お隣さんがプランターにゴーヤの種を放り込んでおいたら、こんなに育ったということでした。来年は、ゴーヤを育てようかと云っています。

-
2010年08月の花
今年の此の猛暑の中相国寺の庭に晩夏から初秋の花と言われている芙蓉の花が早くも咲きはじめました。
逢ひにゆく袂触れたる芙蓉かな(日野 草城)

-
2010年07月の花
額紫陽花
咲き初めは白く、日と共に青紫や紅紫などに変化していくことから七変化ともいいます。アジサイの原種といわれています。
この頃の雨読晴読額の花(鷹羽 狩行)

-
2010年06月の花
初夏に咲く、風車の花は、鉄線花の兄弟といわれています。
見分け方は、花びらの数で、鉄線は6弁で風車の花は8弁です。ふつう花びらと思っているのは、じつは、がくなのですが、花びらと思っているほうが、自然に思えます。

-
2010年05月の花
晩春を彩る藤が、今年は長引く寒さのため、咲くのが遅れているようです。
中村刺繍の近くのお家で、鉢植えで、奥さんが、丹精された藤が咲きました。
藤の房 吹かるるほどに なりにけり(三橋 鷹女)

-
2010年04月の花
平安女学院有栖館の桜です。
醍醐寺の桜の中でも特に有名な桜の直系血縁関係の桜を1952年にこの場所に移植したものと言われています。

-
2010年03月の花
白桃や莟うるめる枝の反り
芥川龍之介御所散策中に撮りました。白桃です。
ピンクの桃はまだ蕾でした。
間もなく開きはじめるはずです。
-
2010年02月の花
2月7日京都では珍しい雪の朝を迎えました。
そんな日、北野天満宮では、紅梅、白梅が見事に咲き始めました。
天満宮では、受験生合格祈願のお参りが絶えません。

-
2009年12月の花
我が家のすぐ近くの妙蓮寺と言うお寺に御会式桜が寒さに耐えて咲いています。
桜と言っても四月に咲くような見事なものでは有りませんが、可憐さがとても良い物です。
十月頃から翌年の四月まで咲くそうです。この妙蓮寺は、芙蓉で有名なお寺です。又芙蓉の頃に写真を撮らせてもらいます。

-
2009年11月の花
紅葉の美しいのは晩秋ですが、冬紅葉といって、寒さが増して又一段と紅が濃くなり美しいものです。
極めたる 色はどの色 冬紅葉
稲畑 汀子冬紅葉 冬のひかりを あつめけり
久保田 万太郎
の俳句が有ります。
-
2009年10月の花
前回に続き秋の七草の一つ藤袴です。
なかなか実際に見る機会の少ない花ですが、京都の上京区役所の前に「これが本当の原種です」と書かれて二鉢の藤袴が有りましたので見て下さい。
別名を「かおりぐさ」とも云います。藤袴手折りたる香を身のほとり
加藤三七子
の俳句が有ります。
-
2009年9月の花
常林寺の萩
萩という字は、草冠に秋と書くように、秋を代表する花です。
万葉の時代から、最も愛された秋草です。
芭蕉の有名な句にも、萩を読んだものがあります。一ツ家に遊女も寝たり萩と月
芭蕉
-
2009年8月の花
今日の幸せを約束してくれるかのように、朝露にぬれ、すがすがしく咲きます。
夏の花と思っていましたが、万葉集の山上憶倉の秋の七草の詩に、アサガオが、出てきます。

日本刺繍のあれこれ、京都の豆知識など、紹介しています。